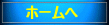江戸幕府は貨幣制度も全国統一したものの、甲州地方に限って領民の強い要望により、武田氏以来の甲州金の発行を許さざるを得ませんでした。 甲州金は、江戸末期まで続いたそうです。
甲州地方はこの間、浅野氏、平岩氏、徳川忠長(家光の弟)、徳川綱豊(6代将軍)、柳沢吉保などが歴代の領主でしたが、左の貨幣発行ころ以降は天領となっていました。
15.1mm 3.7g
(このコインは、講談社の「再現日本史.江戸Ⅱ⑤」に掲載されました。)

元文元年にそれまでの享保小判・一分金に代わって元文小判・一分金が発行されました。金の含有量がそれまでの56%になりましたが、これは元禄の改鋳より悪いものでした。
表の左肩に元文の「文」字があります。
一分は一両の1/4です。一分は、大工さんの日当の5日分にあたる時代でしたから、現在の4~5万円くらいの価値でしょうか。
15.7×9.1mm 3.25g 品位 金653/銀347 鋳造高は小判と合わせて1743万両

一朱は一分の1/4です。朱は金貨の単位ですが、銀座が発行しました。
「南鐐」とは品位の高い銀のことです。
16.2×10.1mm 2.63g 品位 銀989/銅9 鋳造枚数 約1.4億枚

江戸時代の銀貨は、定量ではなく重量の一定でない秤量貨幣が主体でした。大きいものから、丁銀(150g前後)、豆板銀(5g前後)、そして露銀(1g前後)と呼ばれています。
左の品の表には天保の「保」字があります。
この露銀は銭に換算すると35文、二八のそばを2杯食べられます。
7.6mm 1.3g 品位 銀261 鋳造高 丁銀・豆板銀と合わせて18万貫

豆板銀の中には、大黒さんの絵が描かれているものがあります。 銀座の支配人が大黒屋常是と言う人だったことにちなんでいます。
銀貨といっても幕末になるとだいぶ品位が悪くなります。この銀貨には銀が13%しか含まれていません。
13.8mm 5.3g 品位 銀135 鋳造高 丁銀・豆板銀と合わせて10万貫

明治政府が、江戸幕府の単位(両・分・朱)を円・銭に改めて最初に発行した貨幣です。
加納夏雄(1828-98)の作品です。伊能忠敬にも匹敵する仕事をした人ですが、それほど有名でないのは残念です。
13.515mm 1.6666g 品位 金900/銀100 発行枚数 196万枚