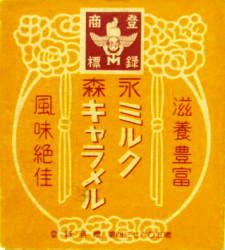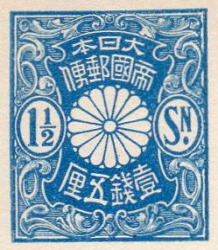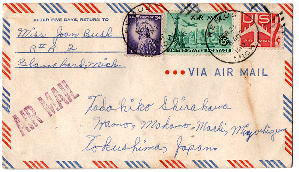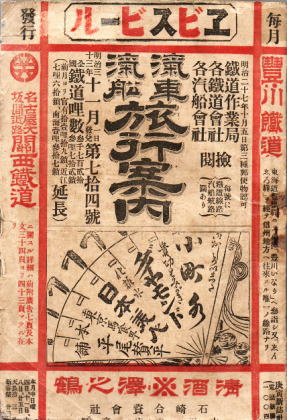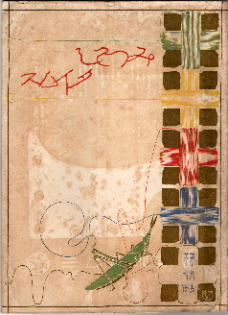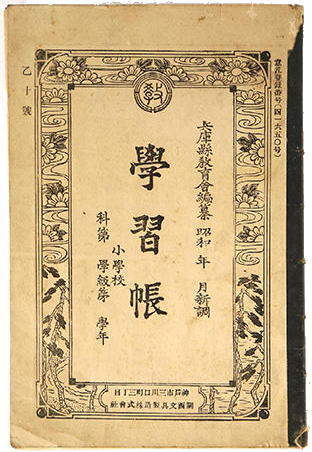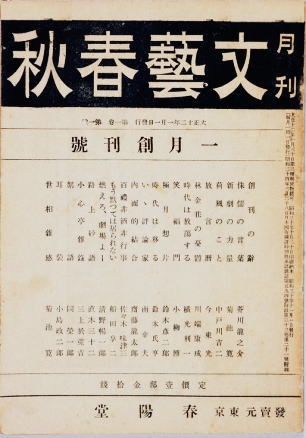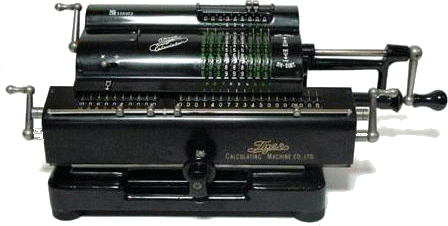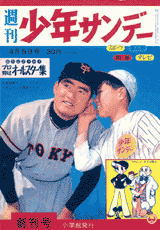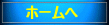2. 食べ物(その2-畜産物・海産物とその加工品)
3. 食べ物(その3-農産物とその加工品)
4. 嗜好品
5. 外 食
6. 給料・賃金(その1-職種共通)
7. 給料・労賃(その2-職種別)
8. 通 信
9. 交 通
10. 反物・衣料品
11. 燃料・照明用品
12. 学用品・日用品
13. 身の回り用品
14. 新聞・書籍
15. カメラ・計算機
16. 戦後の家電
17. サービス
18. 電気・ガス・水道・電話料金
19. 映画・ラジオ・車
20. 娯 楽
21. 高額所得・土地・住宅
22. 木造住宅建設の費用
23. 教育費と進学率
24. 法律などで決まっている値段
25. その他
26. 物価指数
27. 通貨流通高・国家財政・国民所得
28. 貴金属・外為レート
付1. 人口など
付2. 生活インフラの普及率
【参考1】 終戦直後のインフレ
【参考2】 世界の人口の推移
【参考3】 世界主要国の消費者物価指数
【参考4】 マクドナルドのビッグマックの値段
【参考5】 天保~明治 値段史
【参考6】 幕末・明治維新のころ
【参考7】 日本統治時代の台湾と朝鮮
参考文献
・小売物価などは年間(1月-12月)平均値が多いですが、特定商品や公共料金などは年末の値です。
GDP統計などは年度(4月-翌3月)の数字です。 人口(10月1日)、初任給(4月)のように、特定時期の値もあります。
それぞれの注記のところをご参照ください。
・
・数字を( )で囲ってあるのは、参考値、推定値、またはアバウトな数字です。
・原典の数字を丸めたり、1~2銭のように範囲で表示している場合があります。
表示方法は、筆者の嗜好に依存します。
・イタリック体は、暫定値です。
・☆は、補足説明、または蛇足説明です。
・数字の頭に ゚印があるのは、小売価格ではなく、生産者の出荷価格です。
ただし、戦前の資料では、小売価格と卸売価格の区別が明確でないことが多い。
・数字の頭に *印があるのは、平成以降の外税価格です。 消費税率の推移は次の通りです。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・推奨ブラウザは Mozilla Firefox です。
・最終更新:2026年2月。